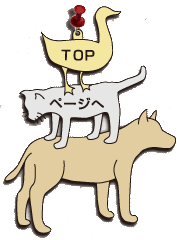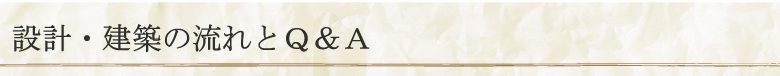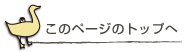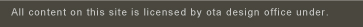![]()
コストに関する質問
工事予算のバランスが分からないのですが?
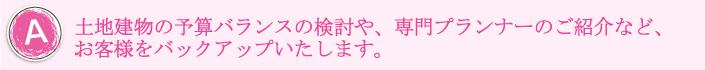
|
「マイホームの夢があるのですが、実際にどこから手をつけていいか分からない」 という方が結構いらっしゃいます。その場合、まずお勧めするのが、「ローン設定がいくらまでいけるかを知ってもらう」という事です。
年収や自己資金により、無理なく返済できる借り入れ額がある程度決まってきます。 そうすれば、いくらを土地代に当て、いくらを建物代に当てれるかが明確になり、 自然と土地の広さや建物の床面積が見えてきます。 このバランスを重視しないと、せっかく進んだ計画や、えがかれれていた夢も、振り出しに戻ることがありますので、まずは専門のプランナーにご相談ください。 土地建物の予算バランスの検討や、専門プランナーのご紹介など、お客様をバックアップ いたします。 |
|
 |
工事費用はどれくらい掛かりますか?
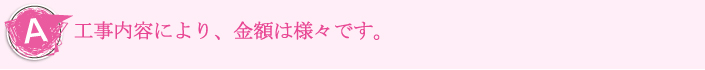
|
様々なケースがありますが、一般的なグレードの住宅の場合、
施工床面積(坪)X60万円 + 外構費+消費税 + 印紙税などの諸経費 ※外構費:建物外部のフェンスや植栽などの費用。 ※1坪≒3.3㎡ 程度です。 ただし、条例による土地の造成や、用途地域の規則による外壁の防火仕様など、どうしてもグレードの高い仕上げにしないといけないこともあります。
使用する材料や、キッチン・浴室などのグレード次第で、坪単価は変わるので、 コストバランスを調整することで、建築費用を抑えることもできます。 例えば、「床材を無垢の木にするために、キッチンをシンプルなものにして減額し、全体のバランスを取る」といったような、金額調整もできます。 |
|
 |
設計監理料がどれくらい掛かるか心配です。
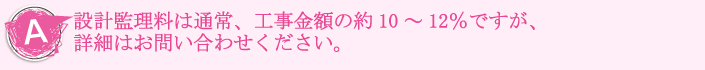
|
設計監理料は通常、請負金額(工事金額)に応じて、総額の何%という方法で決まります。 構造士による計算が必要な物件など、工事の内容によって多少左右しますが、おおむね工事金額の10%~12%程度です。
例えば、「宅地」地目で、地面の高低差が無く、道路などにも問題のない一般的な敷地で、 2階建て木造住宅とした場合で、工事金額が2000万円+消費税の時、
2000万円x10%=200万円+消費税 (リフォームでもほぼ同じですが、既存建物の設計図面が無く、建物の実測をしなければならない場合や、工事金額が1000万円以下の場合は、掛け率が12%~14%程度になる事があります。)
もし、崖地でコンクリートの擁壁や基礎が必要な場合や、3階建て、さらに鉄骨造、コンクリート造の場合などは、専用の構造計算が必要となってきますので、別途約30万円程度かかります。 さらに、敷地の地目が地目が「田」などになっている場合、盛土や切土をして敷地形状を大きく変える場合、市街地調整区域の場合も、開発申請が必要となりますので、開発申請費用が別途かかります。
このように、土地の形状や敷地・建物の内容などが特殊な場合もありますので、まずはご相談下さい。 方法や工法によっては、工事費用がリーズナブルに抑えられ、同時に設計監理料も安くなる事もあります。 できるだけ最適な方法を検討し、ご説明させていただきたいと思います。 |
|
 |
ローンに関する質問
ローンの返済プランを知りたいのですが・・・。
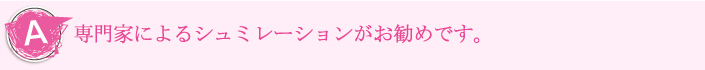
|
ローンを組む前に返済プランを十分考慮しないと、無理なローン設定になってしまい、 将来の生活自体に大きく影響します。 そこで、「ライフプラン」という返済計画が必要となります。
現在の収支のバランスや、家族構成、将来的に必要と思われる金額などを、最近はパソコンで簡単にシュミレーションすることができます。 無料でライフプランを検討してくれる保険会社などもありますので、うまく活用 してください。 オオタデザインから、協力パートナーをご紹介させていただくこともできます。 |
|
 |
フラット35などのローン優遇を使いたいのですが・・・。
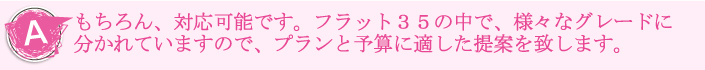
|
以前、フラット35S(20年金利引下げタイプ)を要望されたお客様がいらっしゃいましたが、「20年金利引下げタイプ」は「35S」より、かなりグレードがアップするため、 ローンの優遇金額以上の工事予算が必要となる事がわかりました。
そこで、「フラット35S」で計画を進める方針とし、次に4つある設計基準の中で、 プラン自由性を妨げない「断熱タイプ」を選択しました。 これは同時に、一定の断熱性能をクリアーできるため、住宅エコポイント(30万円分)の収得も見越した選択でした。 結果的に、35Sのローン優遇が受けられ、エコポイントも貰え、エアコンなどの ランニングコストも抑えられる、一石三鳥となりました。
このように、出来るだけお客様の立場に立った視点で、提案させていただきます。 |
|
 |
建築事務所にお願いすると、ローン設定が難しいと聞いたのですが・・・。
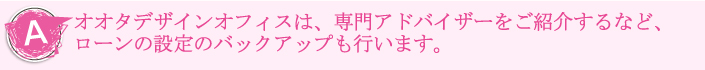
|
銀行によっては、銀行指定の施工業者でないと融資が降りないというところもあります。これは、住宅ローン期間中は、建物は銀行の抵当にあるため、「信用」のある家にしてもらわないと、抵当とみなせないからです。 本当は建築家が入る方が、しっかりした良い建物になるのですが、残念ながら規模が小さい建築事務所というだけで、信用してもらえないようです。
しかし、1つの銀行が不採用でも諦めないでください。世間には多種多様な「住宅ローン商品」がありますので、他銀行や信託などで融資が通る事があります。 |
|
 |
契約や申請などに関する質問
設計契約・工事契約などは大丈夫ですか?
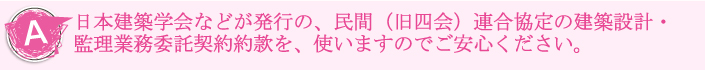
|
一生に一度の住宅の契約は、非常に重要な要素です。 当然、しっかりした契約書を作成し、お互いに納得し合える契約とします。 契約書や約款は、一般的に設計契約で用いられる、民間(旧四会)連合協定の建築設計・ 監理業務委託契約約款(日本建築学会などが発行)を使いますので、ご安心ください。 さらに、施工業者との工事請負契約書の指示や、立ち会いも行います。 |
|
 |
「もしも」の時が心配なのですが・・・。
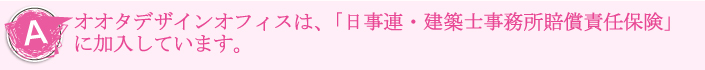
|
細心の注意を払って設計を行いますが、予期せぬ問題が起こることもありえます。 そういった万一の場合に備え、オオタデザインオフィスは、 「日事連・建築士事務所賠償責任保険」に加入しています。
社団法人 日本建築士事務所境界連合会によると、「この保険は、日本国内において行った設計・監理業務のミスに起因して、建築物に外形的かつ物理的な滅失または破損事故が 発生したとき、建築物自体の損害および他人の身体障害・財物損壊について、法律上賠償 しなければならない損害をカバーします。 わけても他人の人身障害については、 特約により万全の備えができました。」とあります。
「もしも」の問題が起こる前に、万全の準備を整えています。 |
|
 |
確認申請はしてもらえますか?またその手続き費用は設計料に含まれますか?
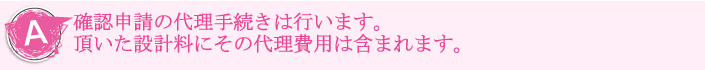
|
確認申請は、本来、建て主自身でも申請可能ですが、建築の専門知識がないと書類作成 ができないので、一般的に建築事務所が代理人として申請業務を行います。
よって、この申請時に掛かる「申請費用」はご負担願いますが、確認申請の代理業務は 設計費用に含まれます。この申請費は、物件の規模や構造、場所などにより異なります。 (木造2階建ての全体申請費はおおよそ、確認申請、中間検査、完了検査の合計で 約10万円です。)
フラット35の申請も同様に、代理申請を行います。 その際、機関発行の申請用紙代(約1500円)はご負担お願い致します。 |
|
 |
新築・リフォーム・リノベーションなどに関する質問
マイホームの具体的なイメージができていないのですが・・・。
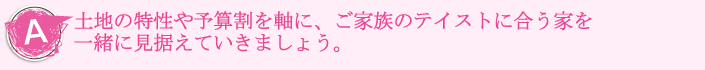
|
皆さん色々なイメージがありすぎて混乱したり、細かい要望ばかりが先行して、 取り止めがなくなってしまったりすることもあると思いますが、大丈夫です。 まずは土地の特性や予算割、さらにそれに合う床面積などをしっかり検討していけば、 必ず方向性が分かってきます。 その中で、ご家族のテイストに合う家を、一緒に見据えていきましょう。 |
|
 |
奇抜なデザインを押し付けたりしませんか?
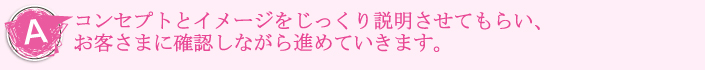
|
建築家は決して、奇抜なものばかり作る訳ではありません。 デザインの方向性については、まずコンセプトとイメージをじっくり説明させてもらい、 お客さまに確認しながら進めていきます。 もちろんそのイメージが合わない時は、他のイメージをご提案させていただきます。
その過程で、機能性や使い勝手を十分検討し、洗練していくとユニークな形になることは あります。 しかしこの形は、決して「奇抜」ではなく、「機能美」であると信じています。 提案内容をご覧になりたい方は、過去に行った物件の提案書をご参考ください。 |
|
 |
木造以外でも設計は可能ですか?
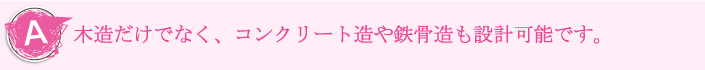
|
コンクリート造や鉄骨造は、構造的な利点や空間が広くなる良さもありますが、 建設コストが高くなってしまいます。 またこれらの構造は、構造専門家による構造計算が別途必要となり、設計料に響いてくる 事もありますので、ご家族の住まわれ方や、プランを総合して、バランスの取れた提案を させていただきます。 |
|
 |
リフォームやリノベーションもできますか?
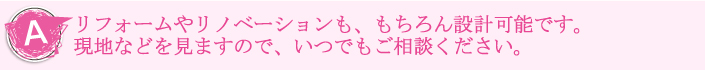
|
既にある建物を再利用するということは、コスト的にも有利に働くことが多く、 環境にもエコです。 さらに既にある柱や梁といった動かせないものの枠組みの中で、新たな空間を考えていく ことは建築家としても腕の見せ所です!色々なアイデアを提供させていただきます。
戸建て住宅のリフォームだけでなく、マンションのリフォームも設計できます。 コンクリートで作られたマンションは無機質になりがちですが、室内に木材や無垢の木を あしらうなど、「人が住みよい環境」を提案させていただきます。 |
|
 |
アフターケアーは大丈夫ですか?
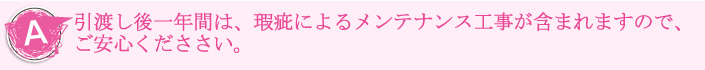
|
建物の不具合については、建築竣工後の半年目と、春夏秋冬を一旦経過した1年目に検査を行い、 瑕疵(施工によるる不具合)に対する処置を、施工業者とともに行います。 さらに最近では住宅施工業者に、住宅瑕疵担保責任保険といった、保証金の確保が 命じられており、消費者の立場が確保されています。 一年検査までの瑕疵によるメンテナンス工事は、本体工事費用に含まれますので、 ご安心ください。
しかし、世の中に、メンテナンスをしなくてよい建物はありません。 どんな建物でも、多かれ少なかれ、何らかの不具合は生じてきます。 お引渡し後は、できるだけ愛着をもちつつ、ご自宅を管理・修繕してあげて下さい。 もし、どうしてよいか分からない問題がある時は、いつでもご連絡下さい。 設計者としても思い入れがありますから、できるだけ協力させていただきます。 |
|
 |